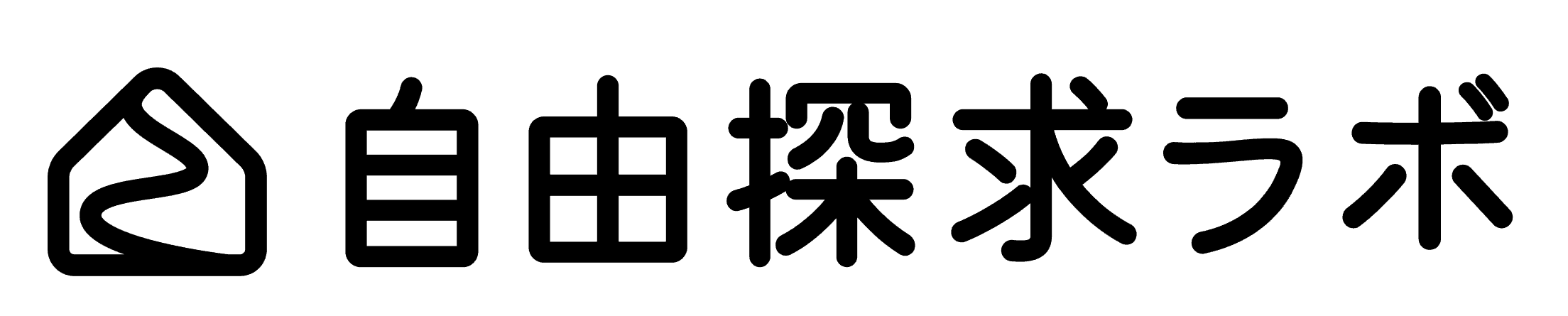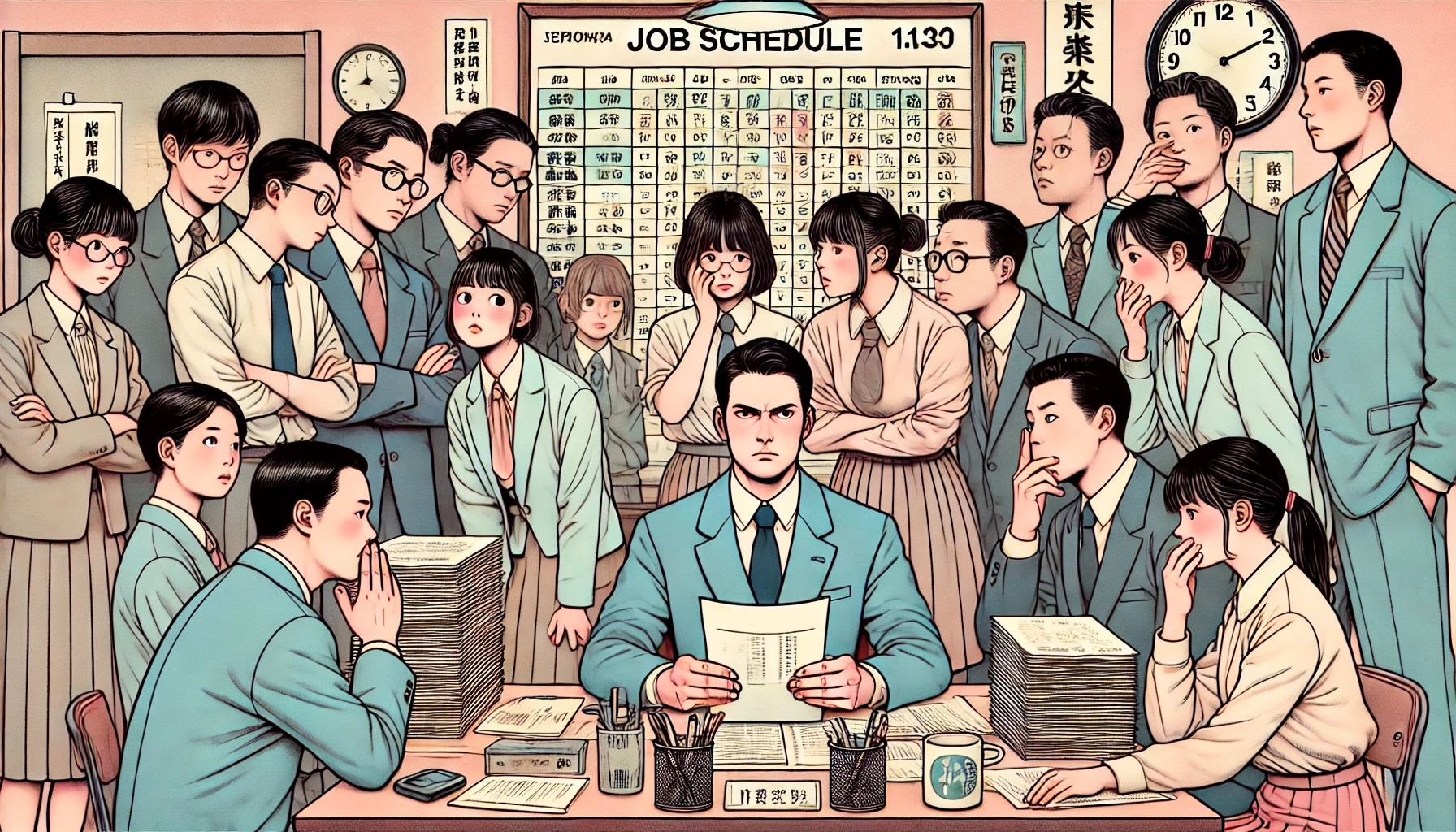はじめに
日本の経済成長が鈍化していると言われることが多いが、その原因は何なのか?大企業で働いた経験を通じて、なんとなく「これが原因では?」と思うことがいくつかあった。
そのうちのひとつが、「UX視点の欠如」 だ。
UX(ユーザーエクスペリエンス)というとデザインの話のように思われがちだけど、本質的には 「ユーザーの体験を最適化し、価値を提供すること」 を指す。でも、日本の企業ではこの考え方があまり重要視されていない。(口では言うが本質を理解されないままのこともある)。
その背景には 「序列主義」や「権威主義」 が根深く関係しているように思う。
つまり、日本の大企業は「お客様第一」と言いながら、実際には「上司第一」「社内調整最優先」になっているのではないか。
UXが軽視される理由
① 顧客よりも社内の合意形成が大事
日本の大企業は 「上司の意向が最優先」 という文化が根強く残っている。
- ユーザーのニーズよりも、社内の調整が優先される
- UXリサーチをしても、「上の人の好み」に合わなければ採用されない
- 「上層部の直感がすべて」とされ、データに基づく意思決定が軽視される
「このUIの方がユーザーにとって使いやすいです」と提案しても、「でも社長の意見はこうなんだ」と一蹴される——そんなやりとりを繰り返しにより、「上の人の好み」に忖度した組織になっていく。
② 広告を打てば売れると思っていた歴史
日本の企業は長年 「広告を打てば売れる」 という考え方に依存してきた。
- 高度経済成長期〜バブル期は、広告代理店が流行を作っていた
- 「ユーザーが求めるものを作る」よりも「テレビCMで売る」ほうが簡単だった
- でも今の時代、広告を打っても「刺さらないサービス」は継続して売れない
にもかかわらず、「とりあえずテレビCMを作ろう」「有名人を起用しよう」という発想が抜けず、プロダクト自体の改善は後回し になりがち。
③ 個人の意見が尊重されにくい
UXとは「ユーザーの体験を重視すること」だけど、日本企業では 「個人の意見を尊重する文化」 があまり強くない。
- 欧米では、個人の権利意識が強く、「おかしいことはおかしい」と言える
- 日本では「上の人が決めたことに従う」文化が根強い
- 「空気を読む」ことが求められ、個人の意見を言うと煙たがられる
「このUIを変えたら離脱率が減る」というデータ付きの実績があったとしても、「でも、ここは古いシステムだから変えられない」「ここの管轄は他の部署だから変えられない」と、何かしらの社内事情によっていったん保留される。保留された課題はいつしか忘れられ、その間に担当が部署異動になり、しばらくしたらまた別の担当が同じ課題の調査から始まるという繰り返し。
このループにより、ユーザー体験の向上に向かうことが極めて困難になる。
3. UXを重視する企業が増えるには?
日本の企業が成長するためには、「顧客中心の視点で意思決定をする」 ことが必要。言うのは簡単だが、実際には組織全体で取り組まないと難しい。ここでは、仮に組織全体がUXを重視する方向に向かうことを指針のひとつにできた場合、実際にどうしたらいいか、の具体策を挙げてみる。
① データを意思決定の中心にする
- 「上司の好み」ではなく「ユーザーのニーズ」で決める文化を作る
- UXリサーチを単なる「参考情報」ではなく、経営戦略の中心にする
- データドリブンな意思決定を定着させる
② 広告に頼らず、プロダクトの体験価値を上げる
- 「広告を打てば売れる」思考から脱却する
- 顧客ごとに最適なUXを描き、長期的に顧客満足を高める
- Appleのように、「プロダクトの完成度そのものをマーケティングにする」
③ 個人の意見を言いやすい環境を作る
- 「役職がすべてを決める」構造を見直す
- 若手や現場のUX担当者が、データを活用して意見を述べられる環境を作る
- ユーザーインタビューや調査の結果を重視して、具体施策につなげる
まとめ:UXを大切にする企業が生き残る
日本企業が成長するためには、「UX視点の欠如」 という課題に向き合う必要がある。
- 「序列主義」や「権威主義」がUXを阻害している
- 「広告マーケティング中心のビジネスモデル」からの脱却が求められる
- UXを経営の中心に据えた企業こそが、これからの時代をリードする
これは個人的な考えだけど、UXを大切にする企業が増えれば、日本のプロダクトも世界で戦えるのではないかと本気で思う。
もちろん、社内調整が不要とは言わない。ただ、社内政治や保身や出世を円滑にするための調整ではなく、「ユーザー体験を向上させるための調整」であってほしい。